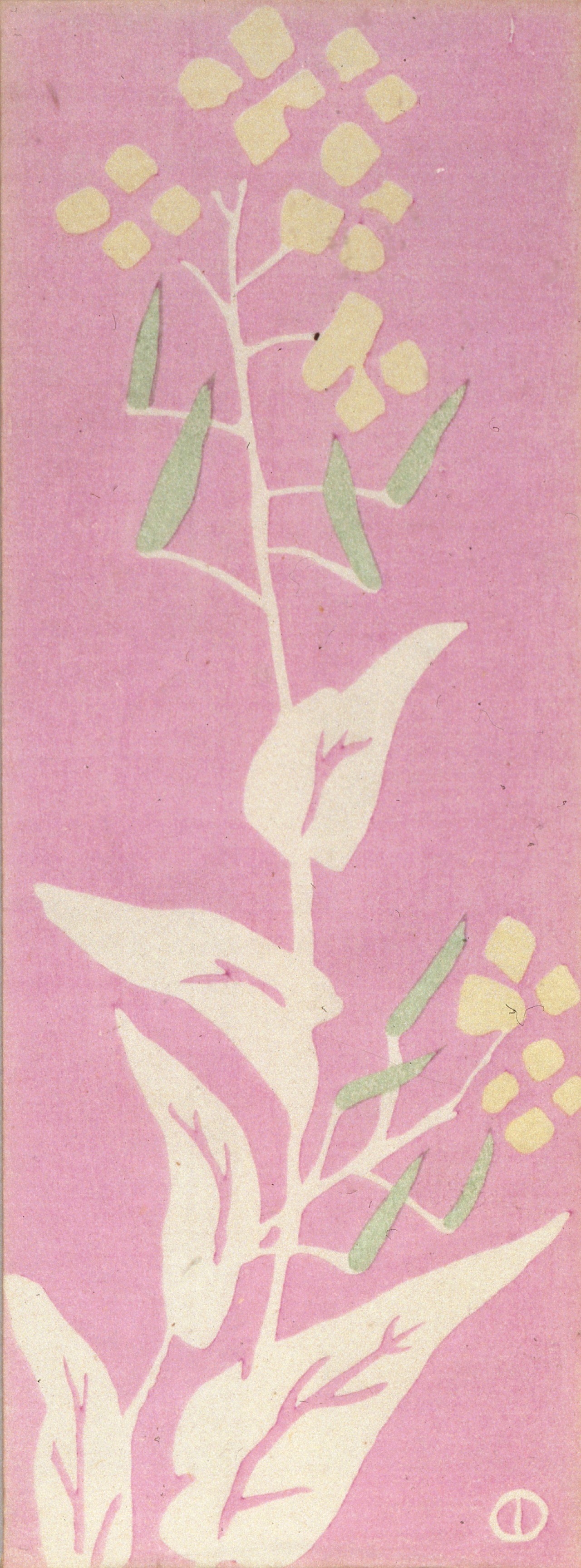2025年07月18日
「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」寄稿記事①
竹久夢二は、1884(明治17)年9月16日、岡山県邑久郡本庄村(現・瀬戸内市)に生まれました。幼い頃から絵を描くのが好きで、画家になることを夢見ていた夢二は、16歳のとき、父親の反対を押し切り上京。早稲田実業学校に籍を置きながら、新聞、雑誌などでコマ絵を発表し、次第にその名が知られるようになります。
1909(明治42)年には、これまで掲載されたコマ絵を収録した「夢二画集 春の巻」を刊行。日本で最初の画集といわれるこの本はたちまちベストセラーとなり、「夏の巻」「花の巻」「旅の巻」「秋の巻」「冬の巻」といった続編が出版されました。夢二は新聞、雑誌、画集という当時の新しいメディアを駆使して、時代の寵児(ちょうじ)となってゆきました。
1912(大正元)年には京都・岡崎公園の京都府立図書館において初の個展を開催。これは当時としては異例の有料の展覧会でしたが、同時期に開催されていた第6回文展(文部省美術展覧会)を上回る入場者数だったといいます。
「林檎(りんご)」は、夢二人気が不動のものとなった画業初期の代表的な1点です。別れた妻である岸たまきをモデルとし、潤んだ大きな瞳とS字カーブを描くしなやかな身体のフォルムなど、夢二が作り出した典型的な美人像を示しています。この独特な風貌の美人は「夢二式美人」と呼ばれて一世を風靡(ふうび)し、「夢二式」という言葉が美人の代名詞として使われるほどでした。
また、夢二はこうした人気を背景に1914(大正3)年、東京・日本橋に自身の版画や書籍のほか、自らデザインした封筒、千代紙、半襟、浴衣、帯などの生活雑貨を販売する「港屋絵草紙店(港屋)」を開店します。西洋で流行していたアール・ヌーヴォーの様式を取り入れた商品群のデザインは当時最先端のもので、港屋は流行の発信地として大繁盛しました。歌人の柳原白蓮(びゃくれん)も東京を訪れるたびに通っていたといいます。女性たちは夢二が描く女性像に憧れ、港屋の商品を日常生活に取り入れることでおしゃれを楽しんでいました。
(大分県立美術館上席主幹学芸員 吉田浩太郎)