展覧会
生誕110年記念 糸園和三郎展 ~魂の祈り、沈黙のメッセージ~

大分県中津市に生まれた洋画家・糸園和三郎は、11歳のときに重い病を患い、以後の学業を断念しました。16歳で上京し、前田寛治が主宰する写実研究所で油絵を学ぶと、1930年には春陽会展で初入選を果たし、やがてシュルレアリスムの有力新人として画壇で注目を集めるようになります。1943年には井上長三郎の呼びかけに応じて新人画会に参加。表現の自由が抑圧された戦時下に画家としての良心を貫きました。戦後は、一時中津に戻って創作を続け、1947年からは自由美術家協会展を中心に作品を発表。現代人が抱える不安や孤独を詩情豊かに描き出した作品は、国内外で高い評価を受け、幅広い人気を博しました。
生誕110年を記念して開催する本展では、初期から戦後の社会性の強い作品群、さらに詩情とヒューマニズムあふれる晩年へと変遷する糸園の画業を代表作により振り返るとともに、作品の構想が描かれたスケッチブックや実際に使われた画材などの関連資料も展示。
常に社会とそこに生きる人々を静かに見つめ、絵筆を持ち続けた糸園の真摯なメッセージを、時代を超えて今、お伝えします。
-
- 会期
- 9月18日(土)~10月31日(日)
-
- 開館時間
- 10:00~19:00(入場は閉館の30分前まで)
※金・土曜日は20時まで開館
-
- 休展日
- なし
-
- 会場
- 大分県立美術館 3階 コレクション展示室
-
- 主催者
- 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館
-
- 観覧料
- 一般800(600)円
大学・高校生 500(300)円
※中学生以下無料
※( ) 内は前売りおよび有料入場 20 名以上の団体料金
※大分県芸術文化友の会 びび KOTOBUKI 無料(同伴者1名半額)、TAKASAGO 無料、UME 団体料金
※障がい者手帳等をご提示の方とその付添者(1名)は無料
※学生の方は入場の際、学生証を提示
-
- お問合せ先
- 大分県立美術館 Tel:097-533-4500
主 催:公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館
共 催:大分合同新聞社、OBS大分放送
特別協力:中津市教育委員会
後 援:大分県、大分県教育委員会、中津市、中津耶馬渓観光協会、大分県民芸術祭実行委員会、NPO法人大分県芸振、西日本新聞社、朝日新聞大分総局、毎日新聞社、読売新聞西部本社、NHK大分放送局、エフエム大分、J:COM大分ケーブルテレコム、NOAS FM
「糸園和三郎展」事前ネット用CM(15秒)
 |
 |
 |
| 令和3年度地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業 |
第一章 新たな表現を求めて
糸園和三郎は1911年、中津市に生まれました。生家は代々呉服商を営んでおり、恵まれた環境に育ちましたが、11歳のとき、当時は有効な治療法が確立されていなかった骨髄炎を患い、以後30歳過ぎまで入退院を繰り返すことになります。地元の小学校を卒業したのちは病気のため進学を断念。16歳で上京し、父の勧めにより川端画学校で絵を学びはじめました。1929年、1930年協会展に出品していた前田寛治の作品に感動し、前田が主宰する写実研究所に入門。翌年には早くも春陽会展で初入選を果たし、1931年からは独立美術協会展でも入選を重ねました。また、この頃は四軌会や飾画、美術文化協会といった前衛的な若手作家のグループにも積極的に参加しており、シュルレアリスムの有力新人として画壇で注目を集めるようになります。1943年には井上長三郎の呼びかけに応じて靉光、松本竣介、麻生三郎らと新人画会に参加。思想統制は厳しさを増し、表現の自由が抑圧された戦時下にあって画家としての良心を貫きました。
戦後は、中津に戻って創作を続け、1927年から自由美術家協会に参加。この頃の糸園は、単純化した力強いフォルムの人体表現が目を引く《鳥をとらえる女》のように造形的な面を強く打ち出した作品を発表する一方、家族の情愛を抒情的に描いたペン画の連作《母子集》なども手がけています。
第二章 社会へのまなざし
戦後しばらく中津で暮らした糸園は、1956年10月、再び上京。1958年からは日本大学芸術学部に勤務し、講師として後進の指導にあたっています。
1950年代中頃から、作品は、《架》や《壁》(1956年)に見られるように人体の簡略が進み、大胆で強靭な構成によるものへと展開。時代の中で疎外され解体されていく人間像が独特の詩情を交えて写し出されたこれらの作品には戦後社会の在り方に対する糸園の厳しいまなざしも感じられます。この2点は《鳥をとらえる女》とともに1957年の第4回サンパウロ・ビエンナーレにも選抜され、糸園は国内外で高い評価を獲得しました。
1968年にはベトナム戦争を主題とした連作《黒い水》と《黄色い水》を発表。同年の第8回現代日本美術展でK氏(鎌倉近代美術館)賞を受賞しています。現地で撮影した報道写真をもとに制作した本作品は、過酷な状況に対する寡黙な作家の、詩情を払拭した直截的な心情表現として注目を集めました。
第三章 内なるものを見つめて
1958年頃から次第に身体の不調を覚えるようになった糸園は、1959年に入院。診断の結果、脳動脈瘤がみとめられたため早速手術の準備にとりかかりますが、「手術が成功しても絵筆を握れるようになるかどうかわからない」という担当医の言葉に、周囲の反対をおしきって退院してしまいます。以後、治療は行わず、死の恐怖と隣り合せになりながらも創作への意欲は衰えることなく、静かに、祈るような制作が続けられていきます。飛び立つ鳥とそれを見つめる青年を描いた《鳥と青年》は、退院直後に手がけたもの。死に直面した自らの心境を描いた糸園の心象風景といえます。
糸園の作品は、心に浮かんだイメージを長い時間をかけて醸成させ、キャンバスの上に写し換えたもので、必ずしも実際に目にしたものではありません。そこには、戦前の作品から一貫してシュルレアリスムへの志向も見られます。一方、技法に注目してみると、形態の簡略化と絵具による絵肌の細かい処理などからは、当時の美術界を席巻していたアンフォルメル(非定型)絵画の影響もうかがわれます。具象絵画を貫きつつも一部に非具象的な要素を取り入れる描き方は、シュルレアリスムの手法とあわせて晩年に至るまで糸園の独特な作風を支えました。
第四章 人間讃歌
1964年、自由美術協会の分裂に伴ってこれを退会した糸園は、以後どの美術団体にも所属せず伊藤廉、牛島憲之、中谷泰らと綾杉会を、また、島あふひ、田中忠雄、山田菊枝ら前田寛治門下の画家たちと濤の会、寺田政明、大野五郎、吉井忠ら自由美術協会時代の仲間と樹展をそれぞれ興して、主にこれらのグループ展で作品を発表してゆくことになります。
1970年代以降の作品には、それ以前の社会的なメッセージ性を強く含んだ作品は影を潜め、老いを題材にした《老婦と子供》や《ブランコの老人》、兄の死を題材にした《阿仁の丘》や《土塊》など、身近な題材を扱った作品が多くなります。描写は以前にも増して精緻を極め、寂莫とした透明な空間に冴えわたる心象世界が描き出されています。
晩年の糸園は目を患い、次第に視力を失っていきますが、その中で繰り返し描いたのが、郷里の小学校の校庭にある楠の大木でした。80歳の時に描いた《丘の上の大樹》はその代表的な作例です。慈愛の光を放ちながら、そこに集う人々をやさしく包んでいる大木が目を引きます。ここには、さまざまな苦しみを乗り越えてきた糸園が、人生の最後にようやく辿り着いた心のありようが、映し出されているようです。
関連イベント
-
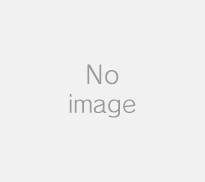
加藤康彦氏(さいき城山桜ホール館長)記念講演会「糸園和三郎 その人と芸術」(※定員に達したため申込締め切りました。)
- 開催日
- 2021年9月18日(土)
- 時 間
- 13:30~15:00
- 会 場
- 大分県立美術館 2階 研修室
-
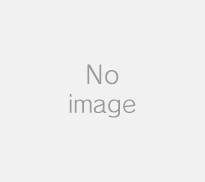
- 開催日
- 2021年9月23日(木・祝) ~ 10月23日(土)
- 時 間
- 14:00~15:00
- 会 場
- 大分県立美術館 3階 コレクション展示室
-
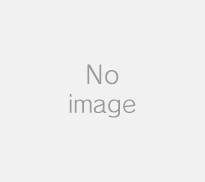
みえない+みえる=∞ ~みんなで美術作品を鑑賞しよう~ vol.3
- 開催日
- 2021年9月25日(土)
- 時 間
- 【午前の部】10:30~13:00 【午後の部】14:30~17:00
- 会 場
- オンライン開催です


